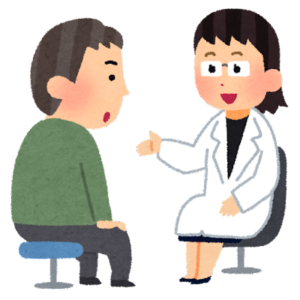手洗いがやめられない 記者が強迫性障害になって
佐藤 陽 (著)
強迫性障害と聞くと、「玄関の鍵やガスの元栓を閉めたっけ?」が最初に思い浮かびましたが、手洗いがやめられないことも代表的なものだと思います。
そんな症状と30年付き合ってきた著者の体験記は同じ病気を抱えている人には参考になると思いました。
本書に出てくる「6割主義」や「できたことに目を向ける」などは、他の精神疾患でも役に立つ内容だと思います。
この病気で本当につらいのは「巻き込み」です。
家族などの身近な人を巻き込むことになる患者本人もつらいし、巻き込まれた家族もつらいです。
本書の最後にある奥様との対談で奥様自身が語っていますが、ある程度症状が落ち着いてきた今の方がつらいというのは驚きでした。年も重ねているし、負担も蓄積していたのだろうと想像できます。
大変な子育てや家事をほとんど一人でこなし、子どもが手を離れたから夫婦で出かけたいと思っても、強迫性障害のことで気を遣うのが大変で近所のスーパーでもヘトヘトになるくらいストレスが強く、外出しないほうがマシと思えてしまうくらいなのだから、ものすごい負担だったと思います。
著者が自分のことでいっぱいいっぱいなのは理解できますが、「僕を置いて娘と出かけるから寂しい」とか「一緒に外出しなきゃ、俺の訓練にならない」といった発言はちょっと奥様への感謝や労いが足りないと感じてしまいました。
さらに、「それなりに生活を送れているわけだから、別に頑張って治さなくてもいいんじゃないかと思えてきた」とか「治そうと思って月1回カウンセリングに行ってるし、薬も飲んでいる」という著者の発言に対しての奥様の言葉も痛烈でした。
「考えが基本、他力本願なのよ。クリニックに通ってるからなんとかなるだろうという感じ。いつも言っているけれど、最終的には自分なんだよ。治せるのは自分しかいなんだよ」という言葉は著者にどれだけ響いているのでしょうか。
もちろん患者本人がつらいのも分かりますが、巻き込まれている家族の気持ちやつらさにも目を向ける必要性がよく分かる対談でした。

手洗いがやめられない ー記者が強迫性障害になってー